「自分の年金、いくらもらえるんだろう?」
そう思ったことはありませんか?
年金の話は「難しそう」「老後のことだからまだ先」と後回しにされがちですが、将来の収入を把握することは、家計を整えるうえで欠かせないステップです。
実際に金額を“見える化”するだけで、
✔ なんとなくの不安が数字で整理される
✔ 必要な準備額や時期が明確になる
✔ 将来の暮らしに対して前向きになれる
という効果があります。
この記事では、「自分の年金額を知る方法」から「受給額を増やす工夫」「将来の家計設計」までを、わかりやすく整理して紹介します。
公的年金の仕組みをざっくり整理
まずは、全体の仕組みを簡単に整理しておきましょう。
日本の公的年金は「2階建て構造」といわれます。
- 1階部分:国民年金(基礎年金)…全国民共通で加入
- 2階部分:厚生年金…会社員や公務員が対象
自営業やフリーランスは「国民年金のみ」、会社員や公務員は「国民年金+厚生年金」の両方に加入しています。
支払う保険料の額や加入年数によって、将来の受給額が変わります。
つまり「どんな働き方をしてきたか」が、年金額を左右するポイントです。
自分の年金見込み額を確認する方法
将来いくらもらえるかは、実際に「自分のデータ」で確認できます。
主な確認方法は次の3つです。
1. ねんきんネット
最も便利なのが「ねんきんネット」。
スマホやパソコンから、最新の加入履歴・見込み額がいつでも確認できます。
マイナンバーカードがあれば、マイナポータル経由で即ログイン可能です。
自分の働き方に応じた将来のシミュレーションも行えます。
2. ねんきん定期便
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」にも、
これまでの加入期間・見込み額が記載されています。
特に50歳以上になると、65歳まで同じ働き方を続けた場合の受給見込み額が載っており、老後の資金設計に役立ちます。
3. 年金事務所での確認
直接相談したい場合は、最寄りの年金事務所で「年金記録照会」を行うことも可能です。
老後の生活設計について相談できる窓口もあるため、不安がある場合は一度訪ねてみるのもおすすめです。
平均的な年金受給額の目安
「だいたいどのくらいもらえるのか」も、家計を整えるうえでの参考になります。
2024年度時点の厚生労働省のデータによると、
- 国民年金(自営業など):月額 約5.6万円
- 厚生年金(会社員など、夫婦2人分):月額 約22万円
あくまで平均値ですが、「一人暮らしなら月6〜8万円」「夫婦世帯で約20万円前後」が目安と考えられます。
一方で、総務省の家計調査によると、65歳以上の無職世帯の平均支出は約26万円。
つまり、年金だけではやや不足するため、「不足分をどう準備するか」が大切になります。
※年金額は年度や物価、賃金の変動によって毎年見直されるため、必ず最新の情報を確認しましょう。ねんきんネットや厚生労働省の公式ページでは最新データが公表されています。
年金受給額を増やす3つの工夫
年金は「もらえる額をただ待つ」だけではなく、自分で増やすこともできます。
1. 加入期間を長くする
保険料を納めた期間が長いほど、受給額は増えます。
特に「免除期間がある人」は、追納(過去分をあとから納付)することで将来の受給額を増やせる場合があります。
なお、未納期間や免除期間があると、その分受給額は減少します。ただし、免除や納付猶予を受けていた場合は、将来の追納(あとから納める)で年金額を増やすことも可能です。追納には期限があるため、早めに確認しておくと安心です。
2. 厚生年金の期間を増やす
パート勤務などで年収・勤務時間が一定以上になると、厚生年金の対象になります。
該当する場合は、国民年金から厚生年金に切り替えることで将来の受給額アップにつながります。
3. 繰下げ受給を活用する
65歳から受け取る年金を、最長75歳まで繰り下げると、1か月ごとに0.7%ずつ増額。
10年繰り下げれば、なんと42%アップします。
長生きを見据えて「少し後に、少し多く」も選択肢です。
ただし、加給年金の有無や税金・社会保険料の影響もあるため、受給開始時期はライフプラン全体を見ながら検討することが大切です。年金事務所や専門家への相談も活用しましょう。
老後資金を整えるためのシミュレーション
年金の見込み額を確認したら、次は「老後に必要な生活費」との差を把握しましょう。
老後に必要な生活費は、都市部と地方でも大きく異なります。家賃・交通費・医療費などの地域差を考慮して、自分の暮らし方に合ったシミュレーションを行いましょう。
例:夫婦2人世帯の場合
- 想定支出:26万円/月
- 受給額:22万円/月
- 不足額:4万円/月 × 20年(65〜85歳)= 約960万円
この不足分をどう準備するかが、家計設計のカギです。
つみたてNISAやiDeCo、退職金の一部活用など、「時間を味方につける仕組み」を整えましょう。
また、年金は個人単位ではなく「世帯全体」で考えることも重要です。配偶者の年金や企業年金を含めて世帯総収入を把握することで、現実的な生活設計ができます。共働き世帯や夫婦間の年齢差がある場合は、受給開始時期のバランスを取ることもポイントです。
さらに、将来は物価や生活費の上昇も考慮する必要があります。公的年金には「物価スライド制度」があり、物価変動に合わせて年金額が調整されますが、実際の購買力は経済状況によって変わる可能性があります。ゆとりを持った資金計画を心がけましょう。
年金に頼りすぎない家計設計
年金は“土台”ではありますが、それだけに依存しすぎない仕組みづくりが重要です。
おすすめは「3本柱の設計」です。
- ① 公的年金:国が保証する最低限の生活基盤
- ② 積立・運用:つみたてNISA・iDeCoなどの自助努力
- ③ 副収入:副業・スキル提供・資産運用による柔軟な収入源
「年金+α」を少しずつ整えることで、将来の選択肢が広がり、不安が減っていきます。
年金を「整える」ことは、未来を整えること
年金を把握することは、単なる数字の確認ではありません。
「未来の生活を自分の手で設計する」行動です。
お金の流れを整える力がある人ほど、不安に振り回されずに生きられます。
特に20〜30代のうちは、「年金なんてまだ先」と感じるかもしれません。ですが、早いうちに自分の将来受給額を把握しておくことで、積立や資産形成を無理なく始められます。“将来の自分への準備”は、早いほど選択肢が広がります。
将来のために、まずは今日「ねんきんネット」を開いてみましょう。
1分でログインし、将来の自分の姿を“数字”で見える化する。
それが、未来の安心を整える第一歩です。
まとめ:将来の安心は「整える力」から生まれる
年金は、未来のあなたの収入の一部。
不安を減らし、暮らしを整えるための重要な情報源です。
- 自分の年金額を知る
- 受給額を増やす工夫をする
- 不足分を今から整える
この3つのステップを踏むことで、漠然とした不安が“見通し”に変わります。
今日の確認が、未来の安心につながる。
「年金を知ること」は、未来の自分への最高のプレゼントです。

これ1冊ですっきりわかる!年金のしくみともらい方 25-26年版 [ 小林労務 ]
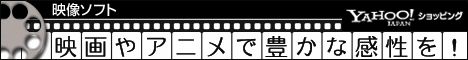
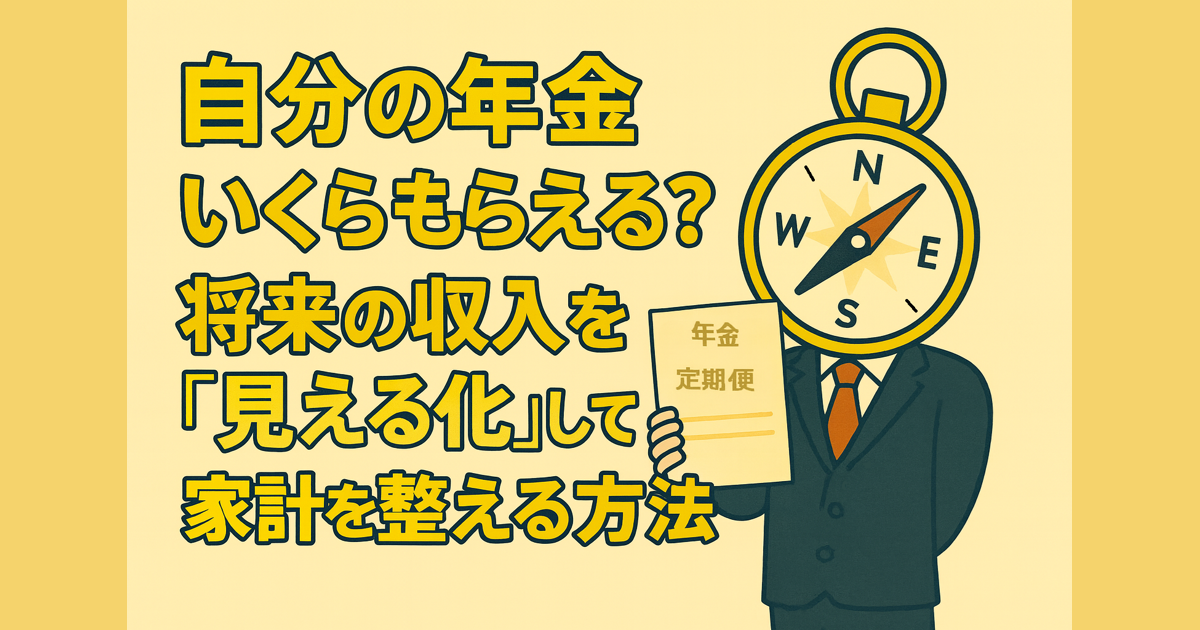
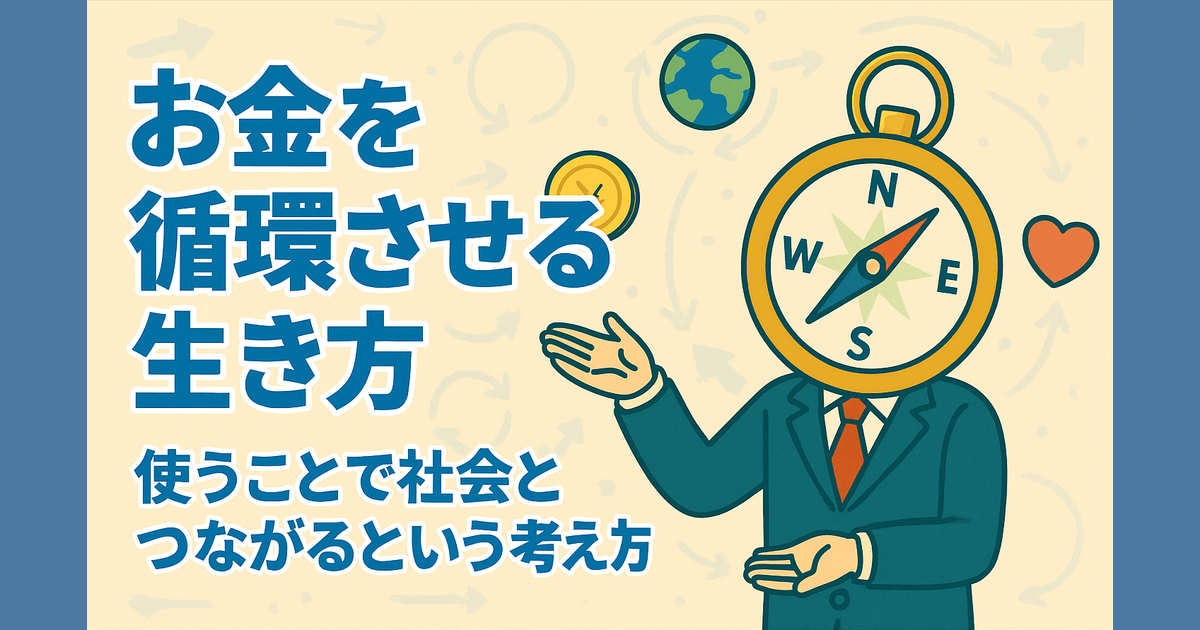
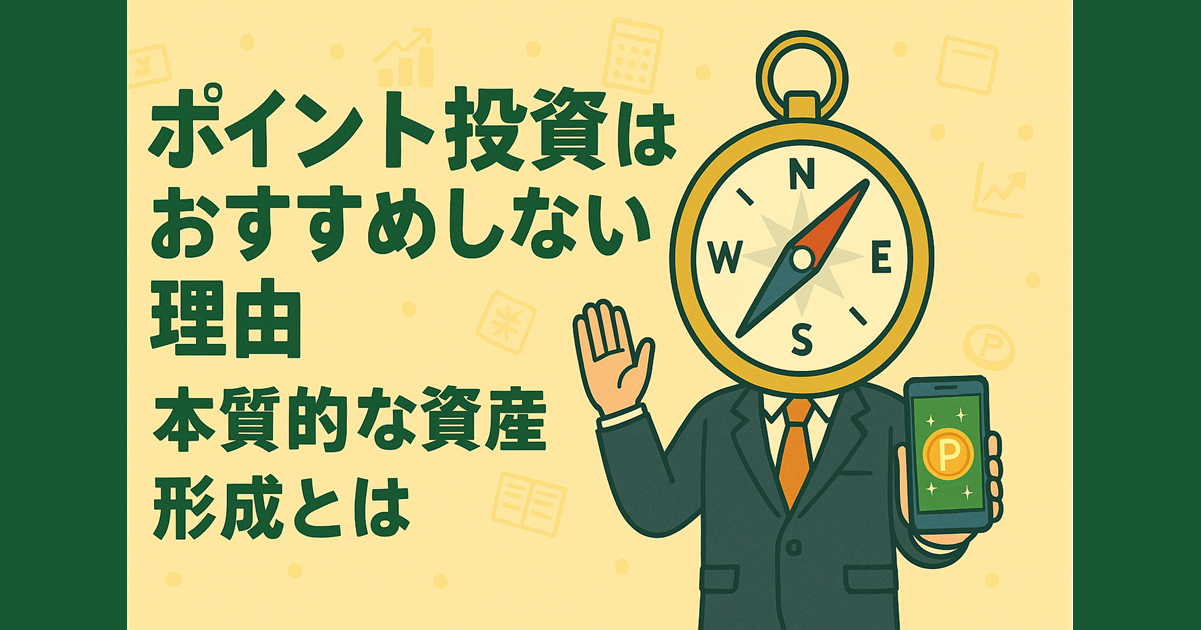
コメント