「給料日からまだ半月なのに、もう財布が寂しい」「毎月赤字になってしまう」――そんな経験はありませんか?
お金の管理ができないと感じている人には、実は共通する特徴があります。自分では気づいていなくても、無意識に同じ行動パターンを繰り返してしまっているのです。
この記事では、お金の管理ができない人にありがちな7つの特徴を解説します。
「もしかして自分も当てはまっているかも」と思ったら、それは改善のチャンス。あなたのお金の使い方を振り返りながら読んでみてください。
お金の管理ができない人の7つの特徴
1. 収入と支出を把握していない
お金の管理ができない人の最も大きな特徴は、「自分が毎月いくら稼ぎ、いくら使っているのかを把握していない」ことです。
「だいたいこれくらい」と感覚で判断していると、実際には想定以上に支出していて赤字になってしまうのです。
例えば、「手取り25万円だから余裕があるはず」と思っていても、固定費(家賃・光熱費・保険料・通信費)で15万円が消え、残り10万円のうち食費・交際費・日用品であっという間になくなる。気づけばクレジットカードの請求が膨らんでいる……というケースは珍しくありません。
収支を見える化しない限り、お金の流れをコントロールすることは不可能です。
2. キャッシュレス決済を無意識に使いすぎる
スマホ決済やクレジットカードは便利ですが、使った感覚が薄いのが落とし穴です。
「タップ一つで支払い完了」する快適さは、同時に「お金を使っている」という意識を鈍らせます。
心理学でも「支払いの痛み(pain of paying)」という概念があります。現金払いでは財布から紙幣が減る感覚が強いため「お金を使った」と実感できますが、キャッシュレスではその感覚が希薄になるのです。
結果として「コンビニで毎日コーヒーを買っている」「ネットで小物をポチポチ買っている」など、積み重なると月数万円単位の支出になることもあります。
3. セールやポイントに弱い
「30%オフ」「今だけ2倍ポイント」といった言葉に心を動かされてしまう人も要注意です。
お得感に惹かれて「必要ないもの」まで買ってしまい、結果的に支出が増えてしまいます。
たとえば、セールで洋服を5着まとめ買いしたけれど、実際に着るのは1〜2着だけ。他はタンスの肥やしになる…。そんな経験はありませんか?
本当に必要なものを必要な時に買うほうが、長期的には家計を整える近道です。
「セールだから買う」のではなく「欲しいと思っていたものがセールになったから買う」に切り替えることが大切です。
4. 貯金や投資を後回しにしている
「余ったら貯金しよう」と思っていても、実際にはなかなか余りません。
多くの人は「まず使ってから残ったら貯める」という考え方をしてしまうのですが、これではいつまで経ってもお金は貯まらないのです。
実際に家計調査でも、先取りで自動積立をしている世帯ほど貯蓄率が高いという結果が出ています。
つまり、お金を貯められる人とそうでない人の違いは「お金を先に確保する仕組みを持っているかどうか」なのです。
5. 短期的な満足を優先してしまう
「今欲しいから買う」「ご褒美だから今日は贅沢しよう」――こうした行動は一時的には幸せを感じられますが、長期的な資産形成にはマイナスです。
お金の管理ができない人は、未来の安心よりも「今の楽しみ」を優先しがちなのです。
もちろん、自分を楽しませること自体は悪いことではありません。問題なのは、それが頻繁に繰り返され、計画性がなくなることです。
「月に一度の外食で贅沢をする」のと「毎週衝動的に外食する」のでは、家計への影響は大きく異なります。
6. 将来のお金の計画を立てていない
「老後にいくら必要か」「教育費はどのくらいかかるか」といったライフプランを立てていない人は、目の前の支出に流されがちです。
将来の見通しを持たなければ、計画的な貯蓄や投資は難しくなります。
特に子どもがいる家庭では、大学までの教育費は1人あたり1,000万円以上かかるといわれています。
「まだ先のこと」と思っているうちに時間は過ぎ、気づいたときには準備不足に陥るのです。
7. 「なんとかなる」と考えてしまう
最後の特徴は、根拠のない楽観主義です。
「これまでもなんとかなったから大丈夫」「将来は給料が増えるだろう」と考えていると、現実を直視せず浪費を続けてしまいます。
しかし、突発的な出費や病気、景気の変動など、将来は予測できないことだらけです。
「なんとかなる」ではなく「どうにかする準備をする」ことが、本当の安心につながります。
お金の管理ができない原因とは?
ここまで「お金の管理ができない人の特徴」を見てきましたが、ではなぜそのような行動をとってしまうのでしょうか?
原因を理解することで、自分に合った改善策を見つけやすくなります。
1. 習慣化できていない
家計管理は「一度やれば終わり」ではなく、毎月・毎週といった継続が必要です。
しかし多くの人は、家計簿をつけ始めても数週間でやめてしまいます。理由は「面倒だから」「効果が見えにくいから」です。
お金の管理は短期間では結果が見えにくいもの。だからこそ、無理のないやり方で「続けられる仕組み」を作る必要があります。
2. 金融リテラシー不足
「お金の基本的な仕組み」を知らないことも大きな原因です。
例えば、保険料や金利、投資のリスクとリターン、固定費と変動費の違い…。こうした基礎知識を持たないと、合理的な判断ができません。
知識がなければ「よくわからないから今のままでいいか」となり、不要な支出や契約を放置してしまうのです。
3. 心理的な要因
お金の使い方には感情が大きく関わります。
ストレスを感じると衝動買いをしたり、寂しさを埋めるために浪費してしまう人もいます。
また「自分はお金の管理ができない」という思い込みが、自己肯定感を下げ、さらにお金の失敗を招く悪循環につながることもあります。
お金の管理を改善する5つのステップ
では、どうすれば「お金の管理ができる人」になれるのでしょうか?
ここでは、誰でも今日から始められる具体的な改善策を紹介します。
ステップ1:支出の見える化をする
まず最初にやるべきことは「現状把握」です。
収入と支出を数字で確認しなければ、改善のしようがありません。
家計簿アプリを使えば、自動でクレジットカードや銀行口座と連携してくれるので手間がかかりません。
おすすめは「Money Forward ME」や「Zaim」など。1週間入力を続けるだけでも、自分のお金の流れがはっきり見えてきます。
「毎日記録するのは面倒…」という人は、まずは固定費だけでも書き出すことから始めましょう。家賃、保険、通信費、サブスク。この4つだけでも可視化すれば、かなりの気づきが得られます。
ステップ2:先取り貯蓄を仕組み化する
「余ったら貯金しよう」は絶対に失敗します。なぜなら余らないからです。
だからこそ、給与が入った瞬間に自動で貯金へ回す「先取り貯蓄」が効果的です。
具体的には、給与振込口座から自動で別口座へ振り替える設定をするのがおすすめ。
毎月2万円でもいいので、自動的に積み立てる仕組みを作れば「貯金できない人」から確実に脱出できます。
ステップ3:固定費を見直す
節約と聞くと「食費を減らす」「光熱費を我慢する」と考えがちですが、それより効果的なのが固定費の削減です。
通信費を格安SIMに変えるだけで年間数万円、保険を見直すだけで数十万円の節約になることもあります。
一度見直せば効果がずっと続くので、ストレスもなく生活の質を下げずに家計を整えることができます。
ステップ4:支出ルールを決める
「生活費は20万円まで」「外食は月3回まで」など、自分なりのルールを設定しましょう。
特にキャッシュレス決済をよく使う人は、1か月の上限をあらかじめ決めておくと使いすぎを防げます。
夫婦やパートナーがいる場合は、共通のルールを話し合うことが大切です。片方が節約しても、もう片方が自由に使っていては管理は成り立ちません。
ステップ5:小さな成功体験を積む
最初から完璧を目指すと挫折しやすくなります。
まずは「1か月家計簿を続けられた」「毎週1,000円節約できた」など、小さな成功を実感することが大切です。
成功体験が積み重なることで「自分でもできる」という自信がつき、習慣化が進みます。
お金の管理はスポーツのトレーニングのようなもので、地道にコツコツ積み上げることが結果につながります。
お金の管理ができるようになるとどうなる?
最後に、改善の先に待っている未来をイメージしてみましょう。
- 給料日前にお金が足りなくなる不安がなくなる
- 貯金や投資が少しずつ増えていく安心感が持てる
- 「本当に欲しいもの」や「やりたい体験」に気持ちよくお金を使える
- 将来のライフイベント(結婚・子育て・老後)にも落ち着いて備えられる
お金の管理とは、単なる数字のコントロールではなく、人生の安心と自由を手に入れるための基盤です。
小さな一歩からで構いません。今日から「整える」行動を始めてみましょう。
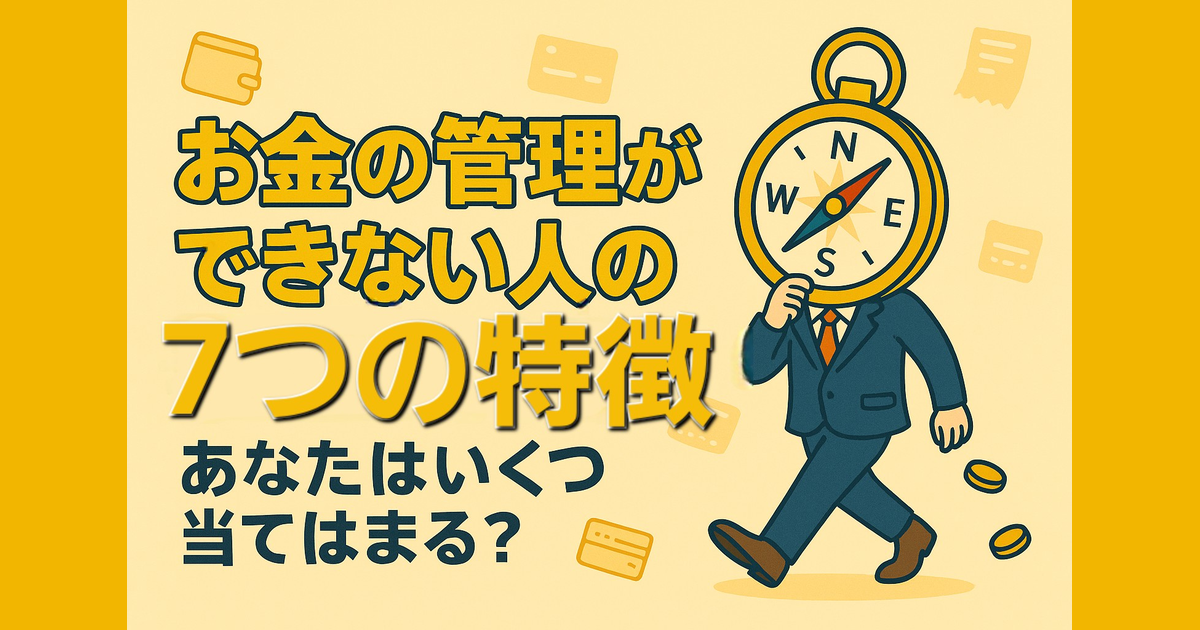
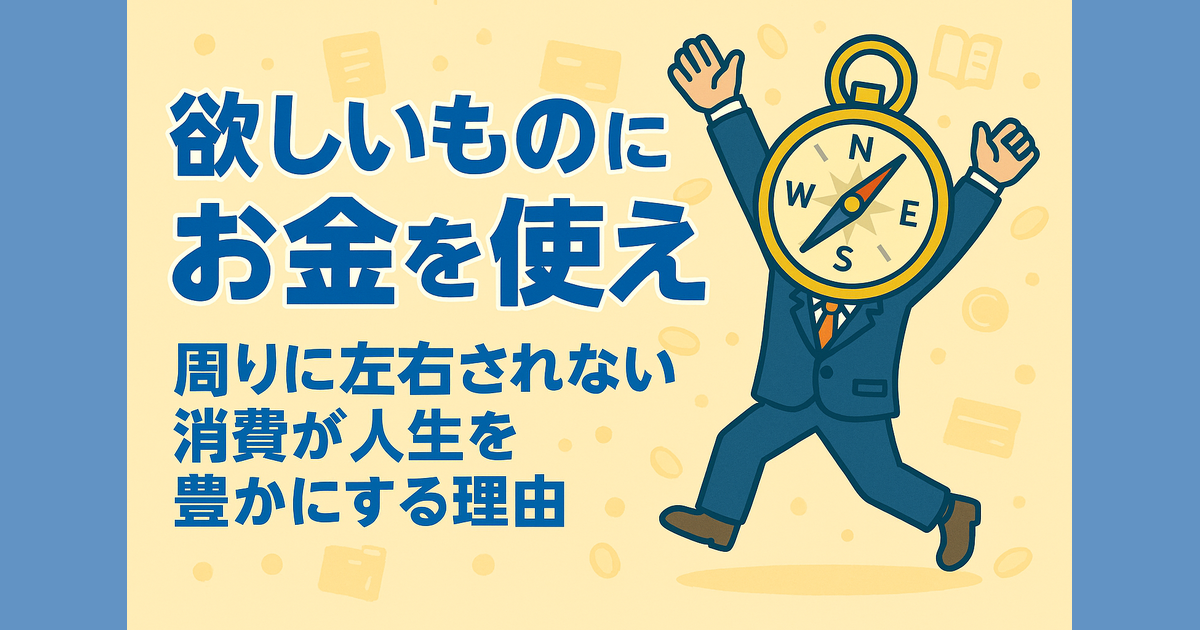

コメント