老後資金の準備や節税対策として注目を集めている「iDeCo(イデコ)」。名前は聞いたことがあっても、仕組みやメリット・デメリットをしっかり理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、初心者の方にも分かりやすくiDeCoの基本から、加入できる人の条件、メリット・デメリット、注意点まで徹底的に解説します。2022年以降の制度改正、さらに2025年6月に予定されている最新改正情報まで補足します。
iDeCo(イデコ)とは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で毎月一定の掛金を拠出し、そのお金を投資信託や定期預金などで運用しながら老後資金を準備していく制度です。
国が制度を運営しているため安心感があり、さらに税制優遇が非常に大きいのが特徴です。
公的年金に上乗せできる制度
日本では会社員や公務員は厚生年金、自営業やフリーランスは国民年金に加入しています。これに上乗せする形で、自分自身が追加で積み立てるのがiDeCoです。
つまり「公的年金+iDeCo」という形で、将来の受け取り額を増やすことができます。
加入できる人
iDeCoは20歳以上65歳未満の国民年金被保険者であれば加入できます(2022年5月の制度改正で拡大)。
立場ごとに掛金の上限が異なります。
- 自営業・フリーランス(国民年金第1号):月額上限 68,000円
- 会社員(企業年金なし):月額上限 23,000円
- 会社員(企業型年金あり):12,000円/20,000円/23,000円(加入状況によって異なる)
- 公務員:月額上限 12,000円
- 専業主婦(主夫):月額上限 23,000円
※2025年6月の法改正により、加入可能年齢は「70歳未満」へ拡大予定です。 施行時期や詳細は最新の公式情報をご確認ください。
iDeCoの3つの大きなメリット
1. 掛金が全額所得控除になる
iDeCoの最大のメリットは、毎月の掛金が「全額所得控除」の対象になる点です。
たとえば年収500万円の会社員が月2万円を拠出すると、年間24万円が所得から差し引かれます。結果として所得税や住民税が軽減され、手取りが増えるのです。
人によっては年間で数万円〜十数万円の節税効果が得られる場合もあります。
2. 運用益が非課税になる
通常、投資信託や株式で得た利益には20.315%の税金がかかります。しかしiDeCo口座内での運用益は非課税。
長期で運用すれば複利効果が大きくなり、老後資金の形成が有利に進みます。
3. 受け取り時も税制優遇がある
積み立てたお金は原則60歳以降に受け取れます。ただし、加入期間によって受け取り開始可能年齢が異なります。
- 加入期間10年以上 → 60歳から
- 8年以上10年未満 → 61歳から
- 6年以上8年未満 → 62歳から
- 4年以上6年未満 → 63歳から
- 2年以上4年未満 → 64歳から
- 1カ月以上2年未満 → 65歳から
さらに2022年4月改正により、受給開始年齢は60歳〜75歳の間で選択可能になりました。
受け取り方法には「一時金(退職所得控除)」と「年金形式(公的年金等控除)」があり、税制優遇を受けられます。
iDeCoのデメリット・注意点
1. 60歳まで原則引き出せない
iDeCoは老後資金準備を目的とした制度のため、積み立てた資金は原則60歳になるまで引き出せません。
そのため「教育費や住宅購入資金などに回す予定があるお金」はiDeCoに入れるべきではありません。
2. 手数料がかかる
iDeCoには加入時、毎月の口座管理料、運用商品ごとの信託報酬などのコストがかかります。
証券会社を選ぶ際には「手数料が安いか」「商品のラインナップが充実しているか」を必ず確認しましょう。
3. 掛金の上限が人によって異なる
会社員でも企業年金の有無によって「12,000円/20,000円/23,000円」と分かれます。
自分の勤務先の制度内容を必ず確認してから申し込みましょう。
※2025年改正で掛金の上限は引き上げ予定です。 自営業は月額7.5万円、会社員・公務員は企業年金との合算で最大6.2万円となる見込みです(専業主婦は現行の2.3万円のまま)。
立場別のiDeCo活用法
会社員の場合
企業年金がない場合、iDeCoは老後資金作りに非常に有効です。
企業年金がある場合は上限が低いため、まずは新NISA(つみたて投資枠)と併用するのが現実的です。
公務員の場合
掛金の上限は月1.2万円と少ないですが、節税効果は確実にあります。給与所得控除後の課税所得が高い人ほど節税メリットは大きいです。
自営業・フリーランスの場合
拠出限度額は最も高く、老後資金を大きく積み立てられるチャンスがあります。国民年金基金と組み合わせるのも有効です。
専業主婦(主夫)の場合
税制メリットは大きくありませんが、老後資金を自分名義で準備できる安心感があります。家計に余裕があれば活用も一案です。
iDeCoと新NISAはどう違う?
iDeCoとよく比較されるのが「新NISA」です。どちらも非課税で運用できる制度ですが、違いがあります。
| 項目 | iDeCo | 新NISA |
|---|---|---|
| 目的 | 老後資金 | 自由な資産形成 |
| 非課税期間 | 60歳以降受給(受給開始は75歳まで選択可) | 無期限 |
| 途中引き出し | 不可 | 可能 |
| 税制優遇 | 掛金控除+運用益非課税+受取時控除 | 運用益非課税のみ |
両方を組み合わせるのが理想です。まずは流動性が高い新NISAを優先し、余裕があればiDeCoを活用するとバランスが良いでしょう。
iDeCoの始め方
iDeCoを始めるには金融機関で専用口座を開設します。SBI証券や楽天証券など大手ネット証券は手数料が安く、商品ラインナップも豊富です。
手続きは以下の流れです。
- 金融機関を選ぶ
- 資料請求・申込書類の提出
- 国民年金基金連合会の審査
- 口座開設完了後、掛金の拠出開始
iDeCoを始める前に確認すべきポイント
- 家計に余裕があるか(60歳まで引き出せない)
- 新NISAとのバランスはどうするか
- 手数料の安い金融機関を選んでいるか
- 投資信託の商品はインデックス中心で分散されているか
まとめ
iDeCoは「掛金控除」「運用益非課税」「受取時控除」という3つの税制優遇が得られる強力な制度です。
2022年以降の制度改正により、加入可能年齢は65歳未満まで拡大、受給開始年齢は75歳まで選択可能、新NISAとの併用も可能になりました。
さらに2025年6月の制度改正により、加入可能年齢が70歳未満へ拡大し、掛金上限も引き上げ予定です。
制度は今後も変化する可能性があるため、最新の情報を確認しながら利用することが大切です。
まずは少額からでも積み立てを始め、老後の安心につなげましょう。


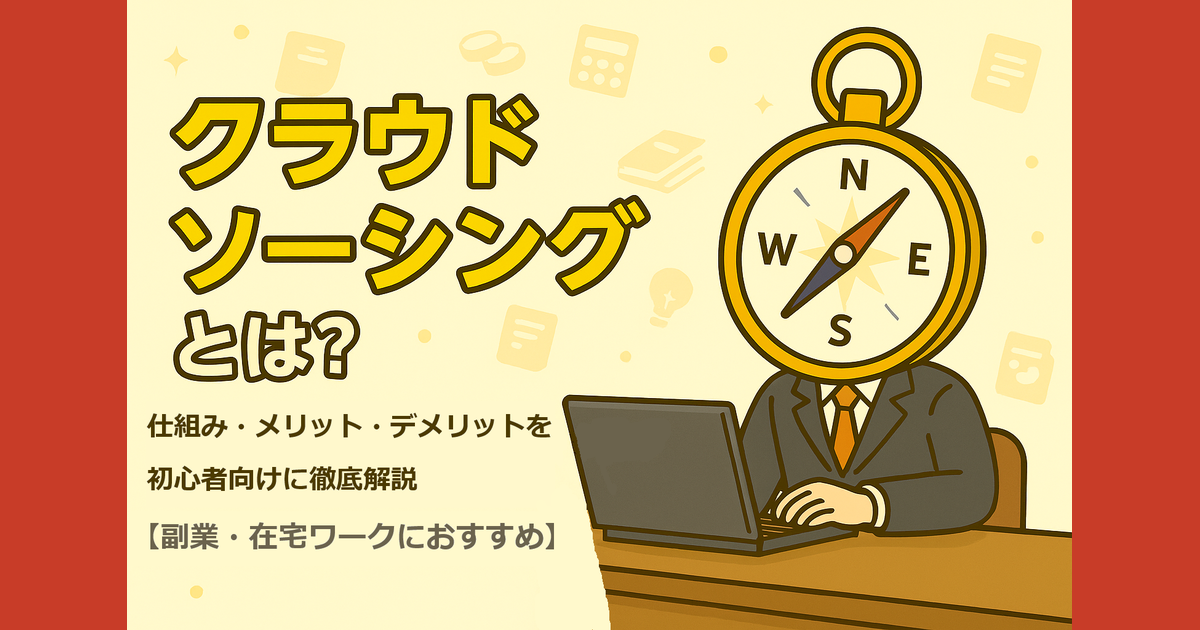
コメント