暴落はいつか必ず来る──それは、過去のデータを見れば明らかな事実です。
しかし、多くの投資家は「暴落でも動じない」「長期投資だから平気」と考えがちです。
ところが実際に資産が20%、30%と減っていくと、ほとんどの人は平常心ではいられません。
そこで気づきます。
「自分のリスク許容度って、思っていたほど高くない」。
これは投資の世界でとてもよくある誤解です。
頭では理解していても、実際のお金が減ると心が追いつかない──このギャップこそ、長期投資が難しい理由です。
この記事では、
・暴落はなぜ必ず来るのか
・なぜ人はリスク許容度を勘違いするのか
・本当のリスク許容度は“想像より低い”理由
・暴落でも折れない仕組みの作り方
を整理して、初心者でも長く投資を続けられる視点をまとめます。
暴落は「予測できない」からこそ必ず起きる
どんな専門家でも、暴落を正確に予測することはできません。
これまでの暴落はすべて“予想外のタイミング”で起きています。
・リーマンショック(2008)
・コロナショック(2020)
・急激なインフレと利上げ(2022)
・地政学リスクによる急落(複数回)
市場は平均して数年ごとに調整局面を迎えます。
・10%以上の下落:5〜7年に1回
・20〜30%:約10年に1回
・大規模暴落は“不定期”だが必ず発生
暴落が「来るかどうか」ではなく、「いつ来てもおかしくないもの」と考えるのが正解です。
なぜ人はリスク許容度を勘違いするのか?
リスク許容度とは、「どれくらいの損失なら耐えられるか」という“心の許容量”です。
しかし、多くの人が自分を過大評価します。その理由は次の3つです。
① 上昇相場で始めると痛みを知らない
含み益が増えていくと、自分が優秀な投資家になったような感覚になります。
この時期に多くの人がこう思います。
「暴落きても買い増しできるし、絶対動じない」
しかしこれは“暴落未経験”の自信でしかありません。
② 損失の痛みは利益の2倍以上
行動経済学の研究で、人は損失の痛みを利益の喜びの2〜2.5倍強く感じることが分かっています。
-10%の損失は、+20%の上昇より重いのです。
理屈では理解していても、感情はまったく別の動きをします。
③ 下落すると未来への不安が一気に膨らむ
資産が減ると頭の中は一気にネガティブになります。
・「このままゼロになるのでは…」
・「続けるべき?やめるべき?」
・「投資って怖くない?」
この心理が、冷静な判断を奪います。
さらに、心理学の観点から言えば、人が下落に弱い理由は「脳の仕組み」にあります。行動経済学の“プロスペクト理論”では、私たちの脳は損失を過剰に恐れるようにできており、含み損を見るだけで本能的な危険信号が発動します。また、「保有効果」により、自分が持つ資産は実際以上に価値があると感じやすく、下落が起きると大きな喪失感につながります。こうした脳のクセが、リスク許容度を冷静に判断することを難しくしているのです。
実際の下落は“想像よりずっと重い”
例えば300万円投資して、20%下落したとします。
損失額は60万円。
数字としては理解できても、
証券口座の画面で「60万円のマイナス」を目にすると、体感は別物です。
証券会社の調査でも、暴落時には
・積立の停止
・売却
・銘柄変更
が急増します。
「長期目線のはずだった」のに、恐怖が勝ってしまうのです。
つまり、リスク許容度は“理屈ではなく感情で決まる”ということです。
過去の暴落を振り返ると、下落の大きさだけでなく「回復までの時間」も投資家のメンタルを試します。たとえば2008年のリーマンショックでは、世界株式は約半年で40%近く下落し、元に戻るまで5年以上かかりました。コロナショックは急落から急回復した特殊ケースでしたが、多くの暴落は「いつ底を打つのか分からない恐怖」と隣り合わせです。画面に表示される含み損は、金額以上に心理的ダメージを与え、冷静な判断力を奪っていきます。これこそが、理論だけでは耐えられない最大の理由です。
暴落に強い投資家は「心が強い」のではなく「仕組みが強い」
暴落時に冷静でいられる人は、特別なメンタルの持ち主ではありません。
彼らは、暴落が来ても平常心でいられる“仕組み”を事前に整えているだけです。
その具体例がこちらです。
① 生活資金を6〜12ヶ月分確保している
現金の余裕は、精神の余裕です。
「もしもの時も売らなくていい」
この状態こそ、暴落に強い投資家の土台です。
② 積立額を“心地よい負担”にしている
積立額がギリギリすぎると、下落時のストレスが倍増します。
理想は、
「これなら暴落しても淡々と続けられる」
というライン。
③ 株式比率を欲張らない
株100%のポートフォリオは、上昇時の伸びは大きくても、下落時のダメージも最大。
債券や現金を組み合わせることで、下落の痛みを自然に抑えられます。
④ 相場ニュースを見すぎない
暴落時にニュースを追い続けると、不安が何倍にも膨らみます。
見る回数を減らすだけで、感情の波が抑えられます。
⑤ ルールに任せて自動化する
・毎月の積立
・アセットアロケーション
・リバランス時期
これらを「仕組みに任せて淡々と続ける」ことが、長期投資の勝ちパターンです。
特に効果が大きいのが「自動化」の威力です。自動積立は、感情を排除して淡々と買い続けるため、平均取得単価を下げる“ドルコスト平均法”の恩恵を最大化できます。また、リバランスを年1回などルール化しておけば、暴落時に自然と債券を売り、安くなった株を買うという“逆張り行動”が仕組みとして実行されます。自分の意思で冷静に判断するのは難しくても、ルールと自動化に任せてしまえば、誰でも長期投資家としての行動ができるようになります。
リスク許容度を測るチェックリスト
初心者が暴落時にやってしまいがちなNG行動として、「積立を止める」「損切りする」「その後に相場が戻ってきても買い戻せない」というパターンがあります。これは“恐怖で売り、安心で買う”典型的な失敗サイクルです。一度このサイクルにハマると、投資をやめたくなるほど精神的に消耗します。大事なのは、暴落が起きたときに自分がどう行動するかを事前に決めておくことです。
次の項目に当てはまるほど、あなたのリスク許容度は“高くない”と考えていいです。
□ 生活資金が6ヶ月未満
□ 下落時に積立を止めた経験がある
□ 毎日値動きを見てしまう
□ 株式比率が高すぎる
□ 暴落時に相談できる相手がいない
□ 投資額が生活費を圧迫している
□ 将来のお金の不安が強い
1つでも不安を感じたなら、無理のない投資設計に見直すタイミングです。
まとめ:暴落を「予測する」のではなく「準備しておく」
投資とは、価格が上下し続ける“揺れ”と付き合う行為です。暴落が起きたときに投資を続けられるかどうかは、才能ではなく準備の差で決まります。むしろ、慎重な性格の人ほど、適切な仕組みさえ整えれば長期投資に向いています。大切なのは、相場に振り回されない自分をつくること。そのための土台がリスク許容度の正しい理解なのです。
暴落は避けられません。
しかし、折れないための準備は誰にでもできます。
・暴落は必ず来る
・人は自分のリスク許容度を過大評価しがち
・損失の痛みは利益の2倍
・感情に勝つのではなく、“仕組みで淡々と続ける”
・生活の余裕がリスク許容度を決める
怖がる必要はありません。
大事なのは、暴落が来ても自分を守れるように、今日から仕組みを整えておくことです。
未来の自分が冷静でいられるように、無理のない投資スタイルを一緒につくっていきましょう。

株価暴落 (文春文庫) [ 池井戸 潤 ]
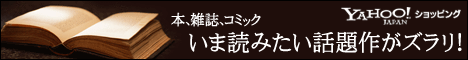


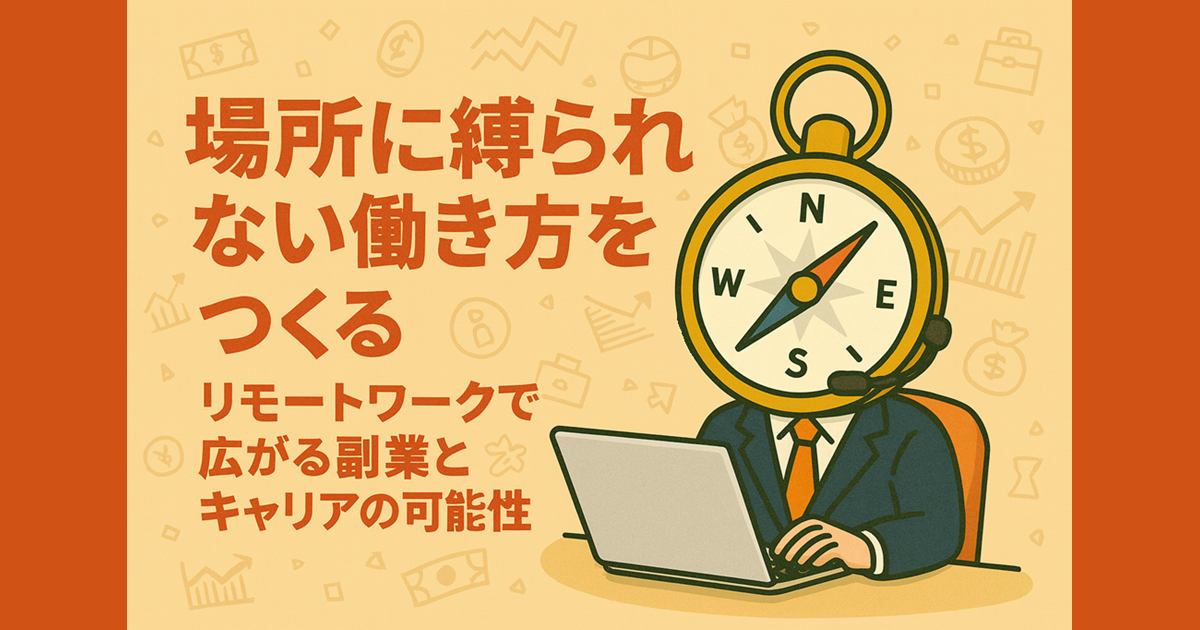
コメント